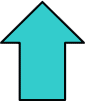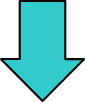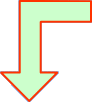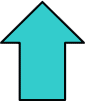
英語科指導方法の工夫改善に関する研究主題
「友だちとかかわり合いながら、
英語表現に親しみ、
進んで英語で表現しようとする
子どもの育成
言語は、論理や思考など知的活動だけでなく、コミュニケーションや感性・情緒の基盤となるものである。言語活動は、豊かなかかわり合いの中でこそ充実し、より質の高いものとなることで、ことばの力を伸ばし、それがまた人間関係を高めていくと考える。
児童が、主体的な学習者となり、自分の考えを確認し深め、自らを確立していくためには、様々な体験と人とのふれあいが欠かせないのである。そこに研究主題の前段部分に「友だちとのかかわり合い」が来る必然性があると考える。しかし、そういった多様な社会経験が今の児童に不足気味であることは否めない。それを補うものとして、学習場面での多様な「友だちとのかかわり合い」が必要なのである。このことは、思考力・判断力・表現力の育成を目指す「ひろしま型カリキュラム」英語科の設立の大きな理由の1つであり、小学校英語科のねらいにも通ずるものである。
さて、授業として具体的には、問題を追及する学習の中で、自分の発見や疑問、思ったことや考えたことを伝え合い、友だちとしっかり意見交流できれば、新たな発見の感動や喜びを得ることができ、自分の考えを再確認したり深めたりすることができる。さらに、今まで気づかなかった友だちの一面を知ることや自分の考えの変容(深まり・広がり)により、相手のよさや自分との違いを理解し大切にしようとする心が育ち、よりよい人間関係の学習集団をつくっていくことができると考える。
英語は、児童にとって、決して身近な言語ではない。言語自体は、主観的なものであるのに対して、身近でない英語は、児童にとって客観的であり、そこに、児童が英語に親しみ、進んで英語で表現しようとする態度を育む大きな可能性があると考える。感情や考察を直接伴う日本語では、少し抵抗のある内容であったとしても、英語表現であれば、その児童の理解や「慣れ・親しみ」による活動として、その抵抗を緩和し、積極的なかかわり合いを生み出すことができるのである。
英語表現や単語にしっかり慣れ親しみ、かかわり合いによる相互評価や自分の高まりを自覚し、英語で表現する楽しさをしっかり味わわせたいと考える。
以上のことから、基礎・基本の確かな力をもとに、友だちとのかかわり合いを通して、主体的に学ぼうとする子どもを育成し、さらに人間関係を高めていきたいと考え、この主題を設定した。
「聞く」「話す」と「かかわり合い」「ことばや文化への気付き」について
英語科の活動の中心は、「聞く」と「話す」であり、他者があって成立することである。つまり、友だち同士のかかわり合いが欠かせない。英語科では、英語による活動を通して、英語を聞いたり話したりする力の基礎を養うとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することをねらいとしている。
その態度により「かかわり合い」から「つながり」が生まれ、生き生きとしたコミュニケーションが生まれる授業づくりを背景に、帯時間と45分の授業を通じて慣れ親しんだ英単語と英語表現の力を土台として、英語を手段とした言語運用能力を育成したいと考える。
また、普段何気なく使っていることばを、英語の仕組みから再認識することより、ことばの成り立ちやその意味を知ることができる。つまり、英語科の学習により、その文化を背景とすることばの成り立ちについて、新たな課題意識が、子ども達の意識の中に主体的に芽生えるのである。そのことは、英語ばかりにとどまらず、日本語の仕組み、さらには、広く言語そのもの成り立ちが、私たちが築き上げてきた文化、さらには、日々の生活や経験に密着しているということの理解につながると考える。
|
英語科指導方法の工夫改善 <研究主題へ> |
|
英語科に関する小中の連携 |
|
会員数の増加 |
|
英語科部会の目的 会員数の増加 英語科指導方法のよりいっそうの工夫改善 英語科に関する小中の連携 |